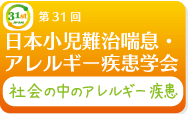第31回 日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会開催にあたって
|
第31回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 |
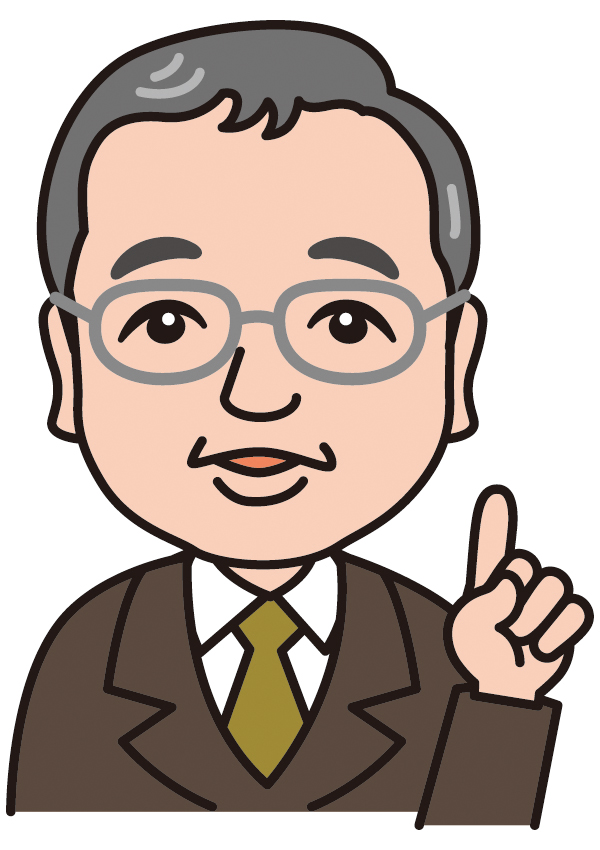 |
第31回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会の開催にあたり、皆さまに謹んでご挨拶申し上げます。
本学会の歴史的な礎である重症喘息児に対する施設入院療法は、愛知県では国立療養所中部病院がその役を果たしていました。私が大学院の頃までは2病棟100人の入院患者がいましたが、今それを若い先生に話すとびっくりされて、年寄り医者を見るような視線を感じます。平成13年、その最後の10人ほどを私たちがお引き受けして、中部病院(現・国立長寿医療研究センター)小児科は幕を閉じました。
この時代の変遷と共に本学会の使命も変わりつつあり、理事会では学会名の変更も含めて、今後の方向性が議論されているところです。その中で、本学会の「伝統」にあまり関わってこなかった私が大会長にご指名いただいたのは、学会の今後の方向性を模索する、試験的な意味を込めてのことと理解しています。
私自身は、小児科2年目からアレルギーの市民団体(現・認定NPO)活動とともにキャリアを積み、その中で育てられてきました。さらに恩師の鳥居新平先生からは、アレルギー疾患を生活環境やアレルゲンから捉える視点の薫陶をうけています。そうした自分の経験を基にして、本学会のテーマを「社会の中のアレルギー疾患」といたしました。
アレルギー疾患は、その原因や解決策そのものが、本質的に社会生活の中にあります。医学・医療の世界が手探りしている問題の本質も、その道の専門家には常識的な事柄かもしれません。医学の世界が作り上げた患者教育や生活指導の「エビデンス」も、その筋の専門家から見たら稚拙な内容かもしれません。アレルギーエデュケーターは、約束のように決められた治療行為を患者に伝えるだけでなく、生活者の視点を患者家族と共有することで、力を発揮して欲しいと思っています。
本学会では、そうした医療の枠の外からアレルギー疾患を見る試みを、あちこちに取り入れてみました。そのために、狭義の医療関係者ではない専門家にも、大勢登場して頂く予定です。私自身も含めて、参加された皆さまの目からウロコが2枚くらい剥がれることを目指して、面白い企画をいろいろ計画中です。
多くの皆さまのご参加を、お待ちしています。